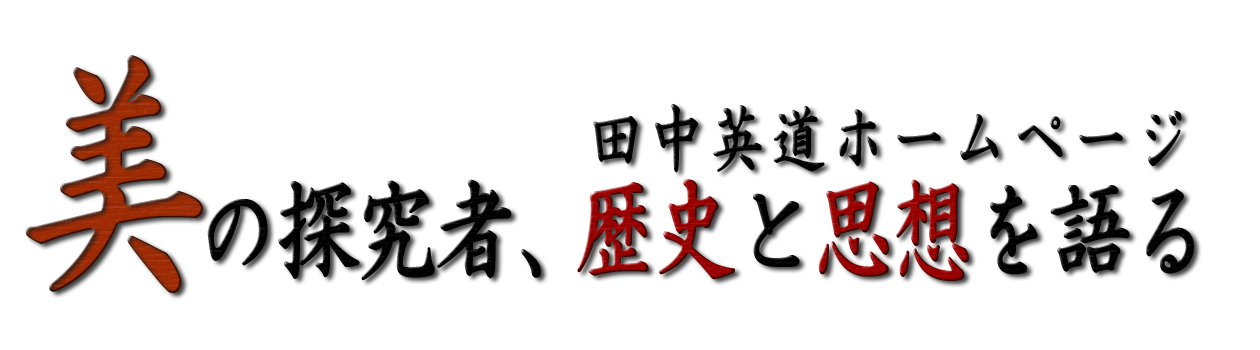著書のお買い求めはこちら(Amazonにジャンプします)。
1970年代までの著書
- 若き日のミケランジェロ
- レオナルド・ダ・ヴィンチ 芸術と生涯
- 冬の闇 夜の画家ラ・トゥールとの対話
など、全11冊
1980年代の著書
- ル・ネサンス像の転換 理性と狂気が融合するとき
- ミケランジェロ
- イタリア美術史 東洋から見た西洋美術の中心
など、全7冊
1990年代の著書
- 天平のミケランジェロ 公麻呂と芸術都市・奈良
- 運慶とバロックの巨匠たち
- 写楽は北斎である
など、全9冊
2000年代の著書
- 国民の藝術
- 新しい日本史観の確立
- A History of Japanese Art
- Leonardo da Vinci
など、全14冊
2010年代の著書
- やまとごころとは何か
- 日本の歴史 本当は何がすごいのか
- 美しい「形」の日本
- 日本人が知らない日本の道徳
など
日本の歴史や文化、思想を深く掘り下げ、また、特に日本と西洋の文化的・思想的な対比を通じて日本独自の価値を再評価する内容が多いです。多くは美術史や歴史学に関する専門家であり、比較文化の視点を重視し、日本文化や歴史を再評価することに力を注いでいます。
主なテーマとしては、以下のようなものが挙げられます:
日本の精神性と文化
例えば、著作『やまとごころとは何か』や『美しい「形」の日本』などでは、日本文化を神道や仏教といった宗教的背景から解釈し、そこに根ざす精神性を論じています。また、『日本の文化 本当は何がすごいのか』などは、日本の伝統的価値観や美意識を重視しています。
日本と西洋の対比
『日本と西洋の対話―一文化史家のたたかい』や『世界史の中の日本 本当は何がすごいのか』では、日本と西洋の文化や歴史を比較し、日本の独自性を浮き彫りにしています。特に、欧米中心の歴史観や西洋思想に対して批判的な視点を示し、日本文化の優れた点を強調しています。
戦後の日本の歴史認識
戦後の日本における歴史認識の問題にも触れており、『戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」』や『戦後日本を狂わせた反日的歴史認識を撃つ』などでは、GHQや左翼思想による影響を批判し、より正確で誇り高い日本史の理解を呼びかけています。
日本の美術と芸術の歴史
美術史的なアプローチでは、特に『日本美術全史 世界から見た名作の系譜』や『芸術国家 日本のかがやき』シリーズなどが、縄文時代から現代に至るまでの日本の美術を論じ、世界的に評価される日本の芸術を再認識する視点を提供しています。
日本人の道徳と宗教観
『日本人が知らない日本の道徳』や『日本の宗教 本当は何がすごいのか』では、日本人の道徳観や宗教観が西洋のそれとどのように異なるのかを探り、日本の自然観や人間観に基づく倫理観を再評価しています。
これらの書籍は、全体として日本文化を誇りに思うべきであるというメッセージを強調し、西洋中心の世界観に対抗する形で、日本独自の歴史や文化的価値を再発見することを目的としています。
2020年代以降の著書
2020年以降の著書は、日本の歴史や神話、考古学、グローバリズム、ユダヤ人との歴史的関係についての洞察をまとめたものが多く、歴史や文化を新たな視点から再解釈する内容が特徴です。代表的な著作には『老年こそ創造の時代「人生百年」の新しい指針』や『左翼グローバリズムとの対決』、『日本国史』シリーズ、『神話と考古学の関係』、『日米戦争の真実』、さらには『日本とユダヤの古代史』や『やはり義経はチンギス・ハーンだった』などがあります。これらの著作は日本史や神話、民族学、政治史、考古学を融合させ、歴史の新解釈や隠された真実に迫るものです。
編著・訳書
- 土星とメランコリー
- ルネサンスの異教秘儀
- ミケランジェロ 彫刻家・画家・建築家
など、全11冊
研究論文
1970年代までの研究論文
- 北斎、広重とヴァン・ゴッホ
- フランス・ルネッサンス美術、ディアーヌの森
- ジャポニスム ― マネとセザンヌ
など、全36編
1980年代の研究論文
- 仙台で発見されたロマネルリの『巫女』図
- ジョット絵画における東洋文字表現
- ローマの支倉常長
など、全38編
1990年代の研究論文
- 大仏師、国中連公麻呂の作品の様式的認定
- ミケランジェロのシスティナ礼拝堂壁画研究
- 西洋美学と『気韻生動』
など、全50編
2000年代以降の研究論文
- 西洋の風景画の発生は東洋から
- 日本におけるイタリア美術研究
- 北斎と遠近法・アナモルフォーズ
など、全23編